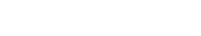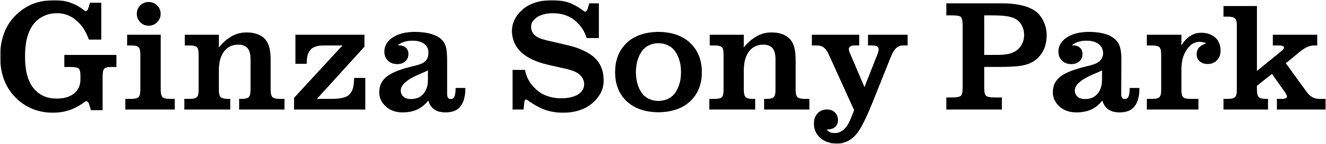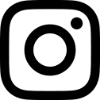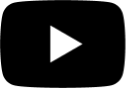今から11年前の2013年にソニービルの建て替えを目的にプロジェクトの構想がスタートしました。
初期段階では公園をつくる計画はありませんでしたが、ソニーらしく大胆でユニークに、銀座の街に新しいリズムを、そして、人々が気分によってさまざまな過ごし方ができるように、という3つのテーマを掲げ、創業者の想いを丹念に紐解いていきました。未来に向けてソニーの個性を形にするにはどうすればよいかを考え続け、導き出した答えがGinza Sony Parkでした。
私たちのプロジェクトでは、公園を構成する重要な要素は「余白」であると考えてきました。
余白の空間はさまざまなものを受け入れ、そして受け流していく。余白があることで空間は変わり続けることができる。だからGinza Sony Parkには多くの余白があります。
このたび無事に竣工を迎え、公園のプラットフォームが完成しました。今はまだ何もない余白だけの空間ですが、グランドオープンしたあと、この余白は、ソニーだけではなく、訪れた人の使い方やアクティビティによって彩られ、この場の楽しみ方も変わり続けていきます。
新しいGinza Sony Parkの今後に、ぜひご期待ください。