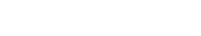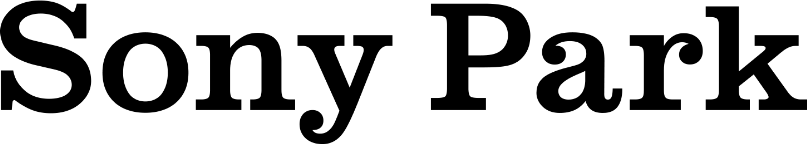去る2022年11月11日から23日の2週間、京都の中心部、京都新聞印刷工場跡地とロームシアター京都の2会場で『Sony Park展 KYOTO』が開催されました。印刷工場跡地の会場では現代美術家の玉山拓郎氏の光をモチーフにした作品が設置されて話題を呼びました。長年使われていなかった印刷工場跡地を"パーク"としてワークさせるのにあたって玉山氏の作品の『光』が大きな役割を果たしました。
今回は、玉山氏に作品と光の関係、そして京都での展示のコンセプトの背景を伺い、あわせてこの場所と玉山氏を『Sony Park展 KYOTO』のために選定した経緯をSony Parkを運営するソニー企業代表取締役社長兼チーフブランディングオフィサーの永野大輔氏が語ります。
インタビュー・文 山本憲資(Sumally Founder&CEO)
パークとアートの相性について。
今回のSony Park展 KYOTO を通じたソニーと玉山さんとの関係って、企業とアーティストとの間にすごくいい関係が成立している一方、属人性と玉山さんの作風に依存する部分も大きく、他で再現するのが難しいのではとも感じます。永野さんの中で企業とアーティストはどう関わるべきかみたいな考えがあれば教えてください。


永野:
Ginza Sony Parkを3年間やってみて、パークとアートの相性っていいなと思ったんです。あと音楽との相性も。もしくはパークとアートと音楽、という3つ。
なぜかは正確にはちゃんと検証できていないんですけど、パークっていうのは余白がすごくある場所で、制約が少なくそこでどう遊ぶかどう使うかが主体者に委ねられている場所、なんですね。特に現代アートは、受け手側に解釈が委ねられているところがある。
ただ逆にパークと商品プロモーションは相性が悪いんです。公園でくつろごうと思っているときにセールスマンに囲まれて、この商品はこれこれこういう特徴がありましてね。って言われても普通の人は気持ちがシャットダウンしちゃいますよね。そうなると人の気持ちと空間とそこのアクティビティがもう完全に分離しちゃってなかなかワークしないです。
アートとか音楽は、来場者に委ねられる側面が大きいですね。来場者が空間を自分のグルーヴで握る中で、アートや音楽を委ねるかたちで差し出すことでうまくハーモナイズさせることができるのでは、という仮説があります。これまで3年間でGinza Sony Parkで企画したアートや音楽のイベントはそういうコンセプトに基づいたこともあって、満足度が高かったです。逆にいうと商品プロモーションに寄ったものはあまり高くなかった。
次の2024年の銀座の新しいビルもコンセプトがパークだし、パークを運営している立場としてはアートとの相性の良さを今度は立体型のスペースで体現していくことができるのではと思っているというのが、経験値から言えるところです。
企業とアーティストの関係。
面白いなと思ったのは、場所作りというときにただビルを建てるだけではなく、 Sony Parkというのはスペースの名称という以上に場におけるソフトであるという話に繋がってくるんだろうなと。
ただそのどう商品を売るか、どうPRするかのためにどうアートを使うか、という観点だと限界があるところを、場所をうまくワークさせるソフトの話と考えると、余白の重要性からからパークっていう概念に繋がってきて、そこで一気にアートとの組み合わせの重要性が増してきますね。


永野:
今までの企業とアートの関係って、やはり商品プロモーションのために使うとか、あとは美術館を作ったりメセナ的な文化貢献みたいな文脈が多くて、企業の本来の営みとアートは分断されていたイメージがあります。
僕はまずやっぱり『場』が必要だなと思っています。Sony Park展 KYOTOは成功を収められたと思っているんですけど、お客さんがたくさん入ったからといって一概に成功でもなく、お客様の満足度が高かったからといってこれまた一概に成功でもないと思っているんですよね。
自分の中でどこが一番評価できた点かというと、銀座でしかこれまでやってきていなかったSony Parkのアクティビティを京都という全くソニーとは関係ないアウェイの地に移植できたところが大きかったです。
Sony Parkの企画は再現性が低いものをやり続けたんですけど、これが京都に移植できたんですよね。概念としての再現性を掴んだところが少しはあったと思います。
生体移植に例えると、家族間でもなく相性のいいドナーからの移植でもない、全く関係のない第三者への移植が実現できたような感覚があって。大阪には(黒川紀章設計の)ソニータワーという施設が昔はあって、ここに巡回するという話であれば家族間の話みたいなもので、そもそも相性がいいわけです。
ソニータワーでなくても銀座と同じような繁華街のギャラリースペースで開催するという方向でも相性は悪くなかったとも思います。ただ今回は認知度も低いはっきりいって超難易度の高いスペースにSony Park展を移植することができた感覚があります。何が成功の鍵だったかと考えると、やはりアートが介在したことで、副反応を起こさないような、あの空間をアクティブにする媒介になってくれた感じがするんですよね。
非常に難しいバランスを実現されていた印象です。いわゆるアートの展覧会でも興行の部分が際立ってもっと商業的にみえたりする部分が気になってしまうことも珍しくないし、難しい塩梅の話だなと思います。
玉山:
大きな企業が関わっていて、そこにアーティストが介入している展示って、僕自身もそうですが、正直ネガティブな印象を受ける人が多いんですよね。でも今回の京都での展示は僕の知り合いもみんな好印象を持ってくれていたんですよ。ちょうどACKというアートフェアの開催期間も重なっていたこともありアート関係の知り合いもけっこう観に来てくれていて。普通だったら誰かがなんとなく、タマちゃんいいの?商業に媚びちゃって大丈夫なの?とか言うんですよ。
でも今回はお世辞ではなくてSony Parkのやってきたことがアーカイブとして展示されている上で玉山拓郎の作品が作品として存在している状態をすごく良かったって言ってくれる人がたくさんいました。僕自身も全体としてすごくいいものができたことを現場で感じられていて、それはとてもすごいことのような気がしましたね。
アーティストとしてのプロジェクトへの立ち位置。
玉山さんの作品は今回のような両立性っていうのを担保できるような、両立を狙って作られているというより、そもそもそういう特性を持ってらっしゃる部分があるんだろうなと思いますが、 そういう部分も含めて、企業とアートの関係みたいなところに玉山さんの考えていることはありますか?


玉山:
永野さん含めて、ソニーの皆さんは僕のことを作品の存在含めて作家としてちゃんと丸ごと受け入れてくれている印象があります。それこそ光の演出だけをお願いできませんか、と言われる可能性もあるじゃないですか。それだと僕はお引き受けしないと思うんですよね。作家としての僕には、作品が存在していることから生まれてくるエネルギーも重要なものですし、そこも含めた関わり方をしないとまず面白いものにならないんですよね。
自分が一演出家として携わるのではなくて、作家として作品をちゃんと成立させた上で、関わってくことに意味ややりがいを感じています。
同じチームだけど、アーティストとしてはチームじゃない部分もあったり。そこの絶妙な距離感は重要な気がしていて。初めから作品ありきの話をしてくださっていたので、不安はなかったですね。
費用はともかくとして、このスペースを1人で借りて展示することは物理的にはできるかもしれないですが、こうやっていろんなメディアとかコンテンツが綯い交ぜになった空間で作品を見せられる機会は、自分ではなかなか創出できないし、ここに至るまですごいエネルギーがやっぱりかかっているわけです。最初は(自分の作品で展示を)喰ってやろうと意気込んでいましたが(笑)、そこに関わっている状態は楽しみの一つで、結果として、自分も全体の中の必要なピースとして属せた気がして。
永野:
この完成形の状態を、ソニーサイドのチームメンバーは誰1人として想像できていなかったんじゃないかと思うんですよね。想像できていたのは玉山さんしかいなくて。そこのイメージを委ねてしまっていたんです。
空間設計の企画・施工をすべて外部の会社にお願いしていたとしたらそうはならない、逆にそんな進め方は許されないと思いますが、今回の空間の最終的なイメージは玉山さんの頭の中にしかなかった。そこをちゃんと玉山さんに主催者である僕たちが委ねられたかどうかが鍵で、そこのリスクをちゃんとこっちで受け止められたところはありましたね。
雑談っぽくなるんですけど、ちょっと遠くに(玉山さんのアイコン的な作品のひとつである)スパゲッティの皿がひとつ壁に貼り付けれていたりも、面白かったのかもしれないなと思っていたんですけど、そういうアイデアは出なかったですか?双眼鏡で見たら見えるかぐらいのところのとこに、とか。
玉山:
うーん、3年前ぐらいの僕だったら、こっそりこういうのも持ってきていて…とか現場で説明しながら、そうですね、はい、やってましたね(笑)。最近は多分大人になってベストな引き具合の塩梅がわかってきました。
永野:
僕は今日の対談を通じて、今回の展示がなぜ成功したのか改めてより深く分析したくなってきました。
普段からアートや建築とかを見ていてソニーにもそれなりに触れているという人たち以外にも今回の展示をいいって言ってくれている人がすごい数いたんですよね。銀座のSony Park展よりも京都の方がおそらく属性が幅広くて。その人たちに対してどこが受けたのかがまだよくわかっていないんですよね。来場者の満足度は99パーセントだったんですが、ヒットモデルの構造を自分たちでも理解しきれていなくて。


Sony Park Mini #23 "Static Lights : Tilt and Rotation"
玉山:
僕は今回の企画はいつか海外でも展示できたらいいなと思っています。国立新美術館の展示は『Museum Static Lights』と名前をつけていて、こちらは世界中の美術館のエントランスでやりたいと思っていて、そもそも輸出しやすいコンセプトにしているんですよ。どこでもできるけど、そこじゃないとできないことも同時に産めると思うんですよね。理想を言えばロンドンのTate Modernのタービンホールでもやりたいですし、ニューヨークのGuggenheim Museumの吹き抜けでもやりたいです。
今回の京都は、美術館ではない空間で大規模にプレゼンテーションした最初の展示として本当に記念すべきものになりました。絶対的に必要な経験値を得られた手応えがあり、今後に結びつけてくためにも重要なアーカイブになったと思います。
『空間にスイッチを入れる』っていうのは、玉山さんにもすっと入っていく概念な気がします。
玉山:
ね、今までその言葉なかなか出てこなかったんですが、『空間をオンにする』というのはしっくりきます。今日はありがとうございました。
永野:
ありがとうございました。

玉山拓郎
1990年、岐阜県生まれ。東京都在住。
愛知県立芸術大学を経て、2015年に東京藝術大学大学院修了。
身近にあるイメージを参照し生み出された家具や日用品のようなオブジェクト群、映像の色調、モノの律動、鮮やかな照明や音響を組み合わせることによって、緻密なコンポジションを持った空間を表現している。近年の主な展覧会に、「2021年度第3期コレクション展」(愛知県美術館、2022)、「Anything will slip off / If cut diagonally」(ANOMALY、2021)、「開館25周年記念コレクション展 VISION Part 1 光について / 光をともして」(豊田市美術館、2020)など。
関連プログラム