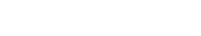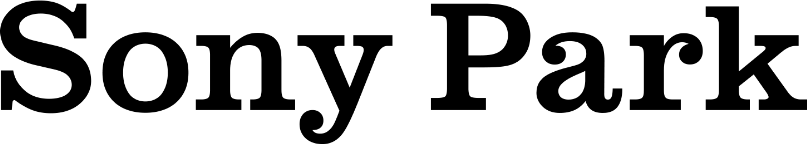去る2022年11月11日から23日の2週間、京都の中心部、京都新聞印刷工場跡地とロームシアター京都の2会場で『Sony Park展 KYOTO』が開催されました。東京のGinza Sony Parkでは期間を分けて展示していた6つの展示を京都では一同にプレゼンテーションし、印刷工場跡地の会場では現代美術家の玉山拓郎氏の光をモチーフにした作品が設置されて話題を呼びました。
京都のインスタレーションに使われた玉山氏の作品の一部が銀座のSony Park Miniでも『Static Lights : Tilt and Rotation』として展示されていた(2022年12月20日〜2023年1月9日)のですが、京都の展示では長年使われていなかった印刷工場跡地を"パーク"としてワークさせるのにあたって玉山氏の作品の『光』が大きな役割を果たしました。
今回は、玉山氏に作品と光の関係、そして京都での展示のコンセプトの背景を伺い、あわせてこの場所と玉山氏を『Sony Park展 KYOTO』のために選定した経緯をSony Parkを運営するソニー企業代表取締役社長兼チーフブランディングオフィサーの永野大輔氏が語ります。
インタビュー・文 山本憲資(Sumally Founder&CEO)
『光を扱う』というプロセス。
今回、京都での展示は『光』がメインで、同時期に国立新美術館で展示されていた『Museum Static Lights』の作品も割と光メインのものだと思うんですけど、 この光の作品は、主役にも脇役にもなる感じがしますよね。ぼーっと歩いてたら作品じゃなくて、ディスプレイ的なものなのかなとも思えるし、ただ作品として観ている人には主役に見えて、周りのものがおまけに見えるし、という。
その両輪のバランスがとれている部分が、今回の京都でのSony Park展のような玉山さんの作品を目的に来る人以外も少なくない展示企画との相性がいいのでは、と思いました。その辺りのバランスへの思いがあれば聞かせてください。


Sony Park Mini #02 "Static Lights : Unfamiliar Presences"
玉山:
光の作品の元を辿ってくと、最初は映像作品だったんですよね。映像作品から漏れ出る光によって空間が変容していく状況に、映像から漏れ出ていたものがどんどん作品空間を構成しているような印象を受けて。
鑑賞者に直接リーチする視覚的なイメージに留まることなく、物質として空間に満ちていくようなイメージをフックにここ数年"光を扱う"ようになりました。そして昨年(2022年)の春に銀座のSony Park Miniで光だけの作品『Static Lights : Unfamiliar Presences』を初めて発表できました。そこがひとつの発端でもあります。
さらにもう1軸あるとしたら、美術史の中で光を扱った作家を鑑みると、(NY郊外にある美術館の)Dia Beaconで永野さんも作品を観たというダン・フレイヴィンは避けて通れないんです。まぁそもそも避ける必要がないんですけど。
やっぱりフレイヴィンがいるからこそ『光の扱い方』が推し進められたところがあって、その上でやっている自覚はすごくあるんですよね。その上でどこまで押し拡げることができるのか、みたいな戦いをこれからしていくんだと思っています。
蛍光灯といういわばホームセンターにも売っているようなマスプロダクトが美術館のような場所にシンボリックに配置されることで、時には空間ごと作品化されながら何か異様な崇高さが生まれる。と同時にやはりただの蛍光灯でしかない。彼がやっていたことはそんなようなことで。


Takuro Tamayama, Museum Static Lights:The National Art Center, Tokyo, 2022, The National Art Center, Tokyo, Installation view, Photo: Kohei Omachi
僕がやっていることで違う部分があるとしたら、たとえば国立新美術館の作品『MuseumStatic Lights :The National Art Center, Tokyo』は実際に建築のその一部をトレースして作っているので、建築と作品の中間に存在していたり、あと空間と作品の中間みたいなポジションでもあったり、どっちともなり得るような存在でありたいな、と。
この作品は、日中はあの躯体がすごく強調されて、すごく物質的でオブジェクティブな存在として、より建築の一部の可能性も生まれてきて、今度は夜になると、フレームの存在感が消えて光の存在が増していく。光もその中の空間に影響を与えるだけじゃなくて、ファサードがガラスなので外からも見ることができる。あれは少し離れた森美術館からも見えるんですよ。それくらい遠くに光が届いている時点であの作品が与えている影響は小さくないなと思っていて。
美術作品として見せるけど、これはただの蛍光灯なんです、という世界とは違う文脈ができているし、建築的なアプローチ、物体としてのデザインなど、いろんな要素が関わって、あの作品は成り立っています。
この年末年始にSony Park Miniで開催していた展示『Static Lights : Tilt and Rotation』で僕が面白いなって思うのは、あの空間の内側にいるときは、ホワイトキューブ的展示空間に作品が設置されている状況なんですが、外から見るとあそこは駐車場の一角が急に変容しているみたいな、割と異様な場所なんです。
美術館の展示室と、パブリックな空間の中間地点的な、妙な間の存在を演出できたなと思っていて、いわゆる美術の文脈だけじゃないところまで鑑賞の可能性を拡げていくことは重要だなと常に考えています。
余白という存在へのフォーカス。
光の作品を空間にどう編み込んでいくか、みたいなところへの意識を伺いましたが、永野さんが玉山さんをフィーチャーしようと決めたきっかけを聞かせてください。


永野:
大阪、京都、神戸といった関西の主要都市でSony Park展の会場を探していたんですが、なかなかピンと来る場所がなくて。ちょうど年明けくらいだったと思うんですが、知り合いを通じて今回の会場を紹介してもらいました。入った瞬間ヤバいな、と。やるんだったら、ここしかないよね、と思いました。
その後、実際あそこでやりましょう、となった時に銀座での展示をそのままインストールして使うだけだとあの場所を借りる意味がないなと。であれば市民ホールやギャラリースペースでやればよくて、やっぱりあそこの空間を使うからにはソニーのアクティビティとあわせてあの空間もお客様に体験してもらいたいというか。普段は非公開なので、京都市民の方もあまり知らない場所なんですよね。その知られざる空間の良さを活かす演出ができないかってことを考えていて。
施工のプランニングを進めていく中で、平場の部分に銀座での展示をプロットできそうだという目処は立ってきたところで、あの空間そのものを演出するプランがなかなか着地できておらずでした。スポットライトを当てるとか、プロジェクションマッピングみたいな案とか色々あったんですけど。 建物へのリスペクトがどうも足りない気がして。
プロジェクションマッピングになったら、コンテンツそのものが主役になっちゃうし。スポットライトやサーチライト的なアプローチもなんだかToo Muchな感じがあり、答えがないまま昨年(2022年)の7月にニューヨークに行ったんですよね。
そこでDia Beaconにはじめて行きました。ナビスコのパッケージ印刷工場跡を美術館にコンバージョンしているのですが、ダン・フレイヴィンの作品が設置された地下の空間に入った瞬間に、空間があの京都の地下のスペースに似ているなと感じました。柱があって、天井が高くて。
で、そこにフレイヴィンの作品が展示されていて。その瞬間、僕の中で、京都の場所のイメージと玉山さんが結びつきました。玉山さんに一緒にやってもらえたら、僕の悩みは解消できるかもと思って、お話をさせてもらったのが経緯です。銀座のSony Park Miniで春先に展示していただいて、そこでしっかりお会いしてその後にお話ししたのが最初ですね。


アート作品そのものというよりも、空間まで巻き込んだ形で作品になっているというのが、玉山さんの作品の特徴だと思っていて。そもそもSony Parkというコンセプトには余白がたくさんある状態が必然といった認識が僕のなかにあります。
余白と展示アクティビティが陰と陽の関係、まさに陰陽図に表されそうな組み合わせであるべきだと考えています。ただ余白は無ということではなく余白として存在してもらわなければならない。余白が存在することで、アクティビティの存在もより際立っていくと思っているんですよ。
京都新聞の印刷工場跡でも同じで、余白とアクティビティがひとつの空間で一緒になって陰陽マークのような関係で。仮にアクティビティが『陽』だとして、余白が『陰』だとした時に、そこをどう演出するか。
存在するためには演出が必要で、ちゃんと『陽』と握手ができるようなものでないといけません。玉山さんの光の作品は、作品そのものを見せるだけではなくて、空間そのものまで取り込んだ形の演出になっていて、空間に作品が来ることによって陰陽の境目が曖昧になる感じというか、陰陽図のように絶妙のバランスで融合するんですよね。
空間に、そしてSony Park展というイベントそのものにスイッチを入れてくれた感じがしました。といっても僕がはじめて完成形を見たのはオープン2日前だったんですけどね。それまでは全然イメージが湧いていなかったのが、照明が入った瞬間、まさにスイッチが入ったと、眼前が開けていく感覚がありました。
長年使われていなかった印刷工場跡の空虚な空間に、玉山さんの作品が組み込まれることで、ある種の魂が吹き込まれるという。その玉山さんのあの作品によって魂が吹き込まれて、ただ魂といっても無機的な世界感は保たれたままで。印刷工場跡というある種の現実的な空間に玉山スイッチが入ることで、非現実な空間が生まれたあとに、Sony Park展の展示をインストールしていくことで現実的な要素を足し戻していくようなプロセスを経て今回の展示空間が生まれましたね。
Sony Park展本体の展示と、玉山さんの作品は、関係としては連続していない気がして、玉山さんの作品にピントを合わせると、他のものが見えなくなる感じがするし、Sony Park展の展示を見ていると、玉山さんの作品が見えなくなる感じもあります。とはいえパキッとしたオンオフというよりはお互い歩み寄った感覚もあり、そこのギャップも面白いポイントです。
アーティストとして培われた『勘』。
施工会社に直接どこどこ風の空間にしてほしいとオーダーすると、絶対今回のようにはならないと思いました。お話いただいたようなプロセスを踏んでいる感じが、空間からも傍から見ていてもほんと絶妙なバランスだな、とちゃんと伝わってきていました。
大企業の最終レベルの意思決定者で、 ここまで凝ったことを考える人ってあんまりいないですよね。それがゆえに実現した空間だというのがよくわかりました。


玉山:
作品を空間に落としていくには、会場のスケールに対して、どのぐらいのボリュームのものがいいかというポイントに綿密な計算が存在しているわけではないんですよね。作家として10年ぐらい活動してきて、徐々に培われた勘みたいのがあります。勘は元々あるんですけど、その勘を自分自身がどのぐらい信用できるかというレベルが、光を扱い続けるというプロセスの中で最近あがってきている感覚も出てきました。
ボリュームがどのぐらいかというのは、最初に下見に行った時点でなんとなくイメージはしていたんですけど、今回は、ここに合わせてすべてを考えたというわけではなかったです。元々連続した回転体のイメージが連なっていく光のオブジェというプランは、ぼんやりとですがそのうちやってみたいものとして頭の中にありました。
最終的に作品を設置したスペースって輪転機が置かれていた場所で。パースが強調されていて、空間の奥行きが感じられる。ふっとそこに一直線の筋が見えたんですね。これはイメージが噛み合ってくるなと。あと回転運動をする輪転機のスペースにああいう円形のイメージは、あ、フィットしているなといった感じで、後からシンクロしてくる部分も今回はありました。


あと作品の色はとてつもなく重要なんです。ただ、僕の中で作品として何色であるべきかみたいなロジックはなくて。色にコンセプチュアルな意味合いがあると、むしろ作品性が制限されてしまうものがあると思っていて。色の理由付けに意味が通りすぎていると、鑑賞者が想像するときにそこから逃れられなくなってしまう気がしていて。
極端にいうと何色でもいいんですけど、やっぱりその場所でどういう効果が起こるか、どういう印象を受けるかみたいなところから最終的に色を判断するための基準は確かに存在していて。そこを経て今回は緑に辿り着きました。
色の存在って簡単に意味付けられるものじゃないと自分としては思っているものの、ただ判断するための材料は自分の中にきっと存在しているなと。ここはピンクの光だとやっぱりダメだったと思うし、赤も青も違っていました。緑だったんですよ。それが正解だったというのには自信があるんですけど、そこに意味としての何かっていうのはないなと。
国立オレンジ新美術館での展示のは、Sony Park Miniでの一回目の展示と同じ色なんです。自分の中で実験的なところもあって、あの空間で見た印象と、空間的により広くなって外からもがっつり干渉していくような場所での印象にどういう差異があるのかと。Sony Park Miniの企画が始まった時点で国立新美術館のプロジェクトも決まっていたので、地続きで同じ色でやってみるというのは、最初から決めていた部分ですね。
あのオレンジは緑以上に有機的な印象が面白かったですね。有機的という意味だけを考えると、緑の方が有機的な色のイメージがあるのにオレンジが見事にはまっていました。
玉山:
それ、ありますね。国立新美術館は黒川紀章建築の最晩年の作品だと思うんですけど、黒川さんの初期の作品は実はそこまで好きじゃないものが多くて。当時は未来的な形状と思われていたような、とはいえ古びていってしまうデザインが多用されている印象で。それに対して国立新美術館は古びない建築なのでは、という気がしています。部分的には黒川さんの癖を感じるところもあるんですが。
初期の作品には色という意味ではブルーとかグリーンが似合っていたかもしれないんですけど、 ああいうふうにガラスのファサードを通して元々の外の緑が見えるようなあの空間には有機的な印象を受ける色が合うんだろうなというのは、今日の会話の中ですんなり思いました。
グリーンの光に有機的な印象が逆にないのは、緑色の光を放つ自然物っていうのが限りなく少ない、というのがあるかも。発光することで色の意味が変わってきているんでしょうね。
鑑賞者の存在への意識について。


永野:
有機の部分に関わることかもしれませんが、作品のある空間に人が存在した時に、人までをイメージした作品・空間・人という形を最初からイメージして制作するんですか?
人がその空間に対して抱く心理的リアクションもあれば、その前段から空間に物質として人が存在する時に、そこで空間がどう成立するかまでイメージされているんでしょうか?
玉山:
人がそれを鑑賞している前提でどういう体験を得られるかはもちろん考えます。鑑賞者が1人で見ていたらまた違うと思うんですけど、そこに別の人がいることで、作品から何かしら影響を受けたある種の"物体"としての人のことも鑑賞するわけですから。
その状況は光の作品に限らず、初期から設定しているものです。作品のモチーフの中に、人とか、生活を匂わせるようなあたたかいイメージを使うことが少ない分、人が物体として存在しているっていうのは 重要なコンポーネントだと思っていて。
鏡を使った作品もあるんですけど、人型のミラーに鑑賞者も映り込むギミックがあったり、そういうものは人が作品世界に存在している前提での作品ですね。

玉山拓郎
1990年、岐阜県生まれ。東京都在住。
愛知県立芸術大学を経て、2015年に東京藝術大学大学院修了。
身近にあるイメージを参照し生み出された家具や日用品のようなオブジェクト群、映像の色調、モノの律動、鮮やかな照明や音響を組み合わせることによって、緻密なコンポジションを持った空間を表現している。近年の主な展覧会に、「2021年度第3期コレクション展」(愛知県美術館、2022)、「Anything will slip off / If cut diagonally」(ANOMALY、2021)、「開館25周年記念コレクション展 VISION Part 1 光について / 光をともして」(豊田市美術館、2020)など。
関連プログラム